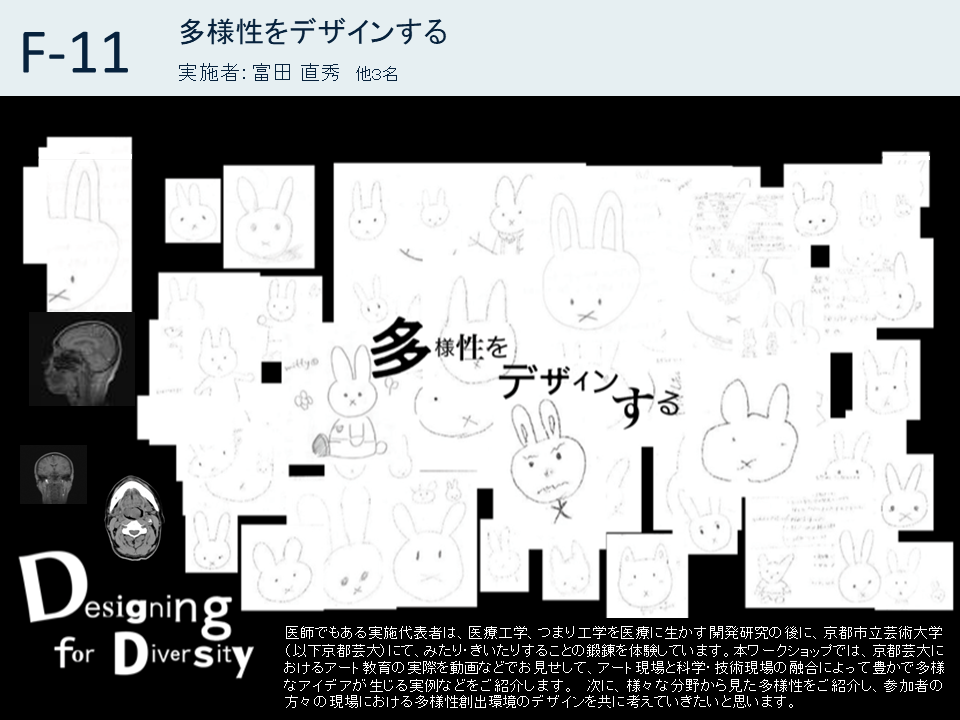ワークショップテーマ
F-11 多様性をデザインする Designing for Diversity
京都市立芸術大学
京都市立芸術大学
多様性という言葉は分野によって様々な意味に捉えられています。たとえば、イキモノは環境に効率的に適合するのみならず、一見無駄な多様性を生じ続けるシステムを維持していることによって急激で致死的な変化を超えて生存し続けています。これは output された多様性の効果であって、その効果はコピー可能です。その一方において、たとえば、平野啓一郎氏は、自己を一つの固定された存在ではなく、複数の分人として捉えることによって、複雑化、効率化しつつある社会の中で、多様性を尊重しながら生活をする新しい価値観を提唱しています。これは、相互作用や input の中で立ち上がる多様な自分であって、この多様性はコピーができない、それぞれ唯一の主体になります。
京都市立芸術大学で行われているアート教育は、美の探求を通してものごとの本質を探る教育ですが、視点を変えますと、上記のようなコピーが可能・不可能な双方の多様性を尊重して、創造性豊かな暮らしを主体的に実践する試みを行っています。近年では企業や他大学にも紹介され、このアート演習に注目が集まっています。
本ワークショップでは、多様性やアート演習の簡単なご紹介を行い、参加者自身の環境における多様性デザインの実践を考案していただきます。
教育目標
- 多様性は、分野によって異なった意味で用いられていますので、まず簡単に用語説明をします。生物における多様性の意味、正常・異常との関係、そうして、コピーの可能・不可能性などを話し合っていきたいと思います。
- 京都市立芸術大学と京都大学の共同実習などで、多様で、非日常であり非現実ではないアイデアが生まれてきた様子などをご紹介します。
- 京都市立芸術大学の総合基礎実技、アート演習などをご紹介します。
- コピーが可能・不可能な双方の多様性をを維持するためのアイデアをデザインし、ミニ動画等を使って発案していただきます。
実施者
| 氏名 | 所属 | 専門分野 |
|---|---|---|
| 富田 直秀 | 京都市立芸術大学 美術学部 客員教授 | 医療工学 |
| 辰巳 明久 | 京都市立芸術大学 美術学部 名誉教授 | ビジュアルコミュニケーションデザイン |
| 舟越 一郎 | 京都市立芸術大学 総合デザイン専攻 教授 | ビジュアルデザイン |
| 石川 陽 | 京都市立芸術大学 美術学部 研究員 | アート教育 |
スケジュール
1日目
午前
- 相互の自己紹介
- 多様性に関するミニレクチャー
午後
- 京都市立芸術大学と京都大学の共同実習の紹介
- 京都市立芸術大学の総合基礎実技、アート演習などの紹介
- 多様性、コピー可能性などにかかわる話し合い
- 課題の検討、発案方法の検討
午前・午後
3日目- 多様性を維持するための幅広い発案
- 発案内容の検討
- プレゼンテーション準備
午前
- プレゼンテーション準備
午後
- プレゼンテーション
その他
| 実施形態 | 対面形式 |
|---|---|
| 時間外活動 | なし |
| 定員 | 6名 |
| 最小催行人数 | 3名 |