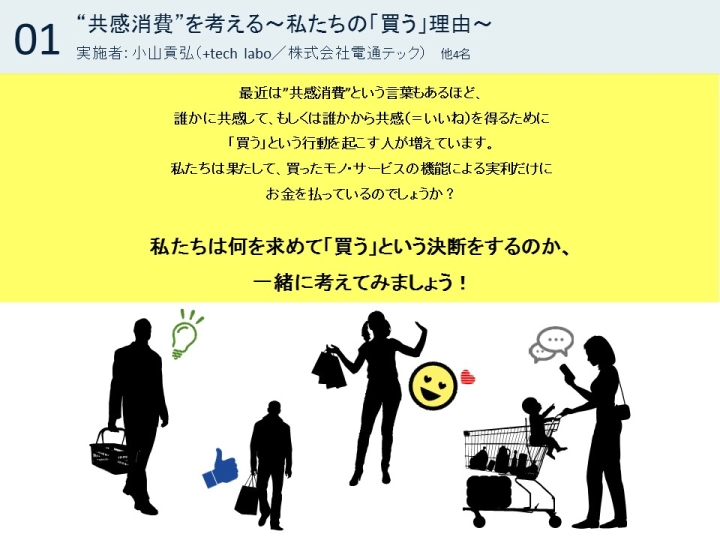皆さんの生活に密着したテーマを設定しました。日々当たり前だと思っている生活を深く観察・考察することで“新たな発見”し、そしてその発見から良質なアイデアを創造していくことを目指していきます。3日間、一緒に考え抜き、創造性を高めていきましょう!
| 氏名 | 所属 | 専門分野 |
|---|---|---|
| 小山 貢弘 | (株)電通テック +tech labo | リテールマーケティング |
| 堀 かおり | (株)電通テック +tech labo | トレンドマーケティング |
| 木下 和也 | (株)電通テック 関西支社 アクティベーション事業部 | デジタル |
| 三浦 優大 | (株)電通テック UX部門 | デザイン |
| 佐々木 梨花 | (株)電通テック OMO部門 | プランナー |
SNSの普及は、生活者のモノを「買う」という行為のあり方を変えた。自らの生活の充足のためというだけではなく、周りの人にシェアしたい、つまり“共感”を得るためにモノを「買う」という流れが生まれている。この“共感消費”は、「インスタ映え」等のコトバに代表され、多くの生活者が実践している。しかし、この“共感消費”の概念は、依然として曖昧なものに思える。一体、何が生活者に“共感”を感じさせて、買いたい・シェアをしたいと思わせるのであろうか?その「正体」は解明されていない。
今回のワークでは、この“共感”の「正体」を探ることからスタートしていきたい。観察・フィードワークを通じて、自らが「共感」したいと考えるモノには、どんな要素が詰まっているのかを考え抜いていく。そして、チームで得られた数々の発見を言語化・構造化していくことで、“共感消費”の「正体」について一定の結論を出していきたい。そして、その結論をもとに、“共感消費”を生活者に呼び起こすために、企業のマーケティング施策はいかにあるべきなのか?をアイディエーションを重ねていきたい。
参加者に「自分の創造性に対する自信」を持ってもらうことを目指していきます。まず、自分の身近にある普段は意識をしていない人・事柄を深く観察・思考することで、隠れていた課題を“発見する力”を身につけていきます。そして、そこで得られた膨大な課題を“抽象化・定義化”して仮説を導いていきます。そして、仮説をもとに“拡散と収束”を繰り返して良質なアイデアを生み出していきます。この一連のデザイン手法をチームメンバーとともに実施していくことで、参加者各人が当初には想像もつかなかったようなアイデアにいきつくことができたという意識を持っていただくことを目指していきます。
- エスノメソトロジー(デザインレクチャー2019 2nd第2回の講義録を提示)
- サービスのデザイン(デザインレクチャー2018 1st第2回の講義録を提示)
【デザイン手法】
- ユーザーインタビュー/観察
- 定義化/構造化
- ブレインストーミング
- プロトタイプ
- チームビルディング
- フィールドワーク(一定金額内で「人にすすめたいモノ」を買いに行く) ※フィードワークの購入費用は当社が負担します。
- 購入した「人にすすめたいモノ」の背景にある思いを個人・チームでインタビュー・議論
- 議論で出てきた数多くの“発見”を収束化させて、「“共感消費”とは○○○○である」と構造化・定義する。
- 昨日の振り返り&生活者の視点で「企業にやってほしい“共感消費”プロモーション」をブレインストーミング。
- 「企業が行うべき“共感消費”プロモーション」をアイディエーション
- 得られたアイディエーションをプロトタイプ&修正
- 翌日の準備
- プレゼンテーション準備(京大時計台)
- プレゼンテーション(京大時計台)