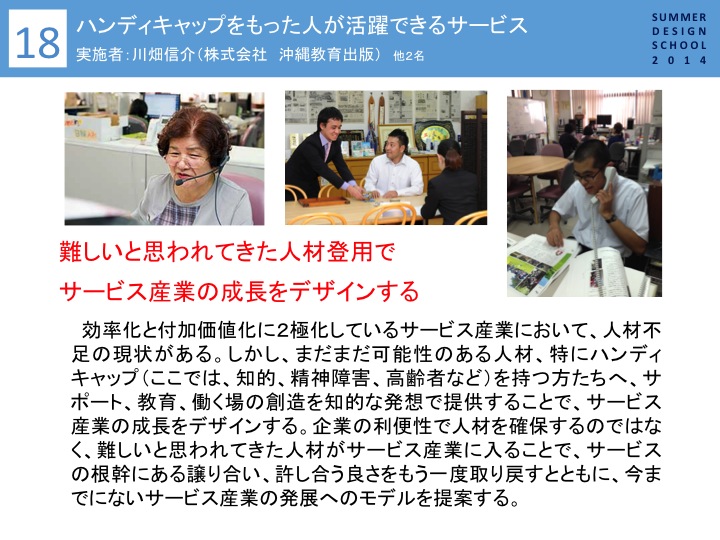テーマ
18 ハンディキャップをもった人が活躍できるサービス
関係者・関係組織
実施者
角谷 恭一(NTTデータ)
川畑 信介(沖縄教育出版)
北野 清晃(経営管理大学院(デザイン学本科生))
田島 瑞希(NTTデータ経営研究所)
山内 裕 (経営管理大学院)
角谷 恭一(NTTデータ)
川畑 信介(沖縄教育出版)
北野 清晃(経営管理大学院(デザイン学本科生))
田島 瑞希(NTTデータ経営研究所)
山内 裕 (経営管理大学院)
課題内容
いま,サービス産業は二極化が進んでいる.一方は,効率重視,出来る限り平易なマニュアル化をし,安い賃金の労働者を活用するというも.もう一方は高付加価値サービスでお客様に喜んでいただけるのでれば,サプライズを演出するためのコストは厭わないというものである.同時に,安い人件費で雇用できる人が減って来ており,どちらのサービスも人材不足になっている.しかしながら,まだまだ可能性のある人材,特に,ハンディキャップ(ここでは,知的,精神障害,高齢者などとする)を持っている方たちにしっかりしたサポートと教育,そして働く場を創造することで,サービス産業に登用することは可能ではないだろうか?そのために,サマーデザインスクールで,ハンディキャップの立場を理解するため,視覚,聴覚などの制限を通して,実際にサービスの可能性をデザインする.
教育目標
参加者が自分たちの理解でデザインするのではなく,ハンディキャップを持つ人の視点を理解することで,デザインする姿勢,方法,事例を学ぶ.実際に参加者に知的障害をもったメンバーに参加いただき,仮説で終わるのではなく,本人が実際にできるレベルまでデザイン化する.
サービス産業は,人がするものだからこそ,人であればどんな人でも可能性があり,加えて成長をデザインできるもの.そのためには,環境整備,人材サポート,そして何より根気強さなど,現代ビジネスのスピード重視型経営においては,真逆の発想である.だからこそ,サービス設計をする人がどれだけ,ハンディキャップをもった方へ寄り添いながらも,仕組み化できるところを知的な発想で突破し,よりよい未来づくりをイメージして欲しい.
サービス産業は,人がするものだからこそ,人であればどんな人でも可能性があり,加えて成長をデザインできるもの.そのためには,環境整備,人材サポート,そして何より根気強さなど,現代ビジネスのスピード重視型経営においては,真逆の発想である.だからこそ,サービス設計をする人がどれだけ,ハンディキャップをもった方へ寄り添いながらも,仕組み化できるところを知的な発想で突破し,よりよい未来づくりをイメージして欲しい.
デザイン理論
- サービスデザイン
- ワークプレースデザイン
デザイン手法
- インクルーシブデザイン
スケジュール
一日目
午前
- 自己紹介など
- 現存のサービス産業についてのディスカッション
午後
- ハンディキャップって?
- テーマ決め
ニ日目
午前
- テーマに沿って,未来のサービス産業設計
- そのサービス産業の中で特筆したものを一つ絞り込み
午後
- 設計したサービスのKFS出し
- ペルソナを作り,イメージ化
三日目
午前
- 発表準備
午後
- プレゼンテーション