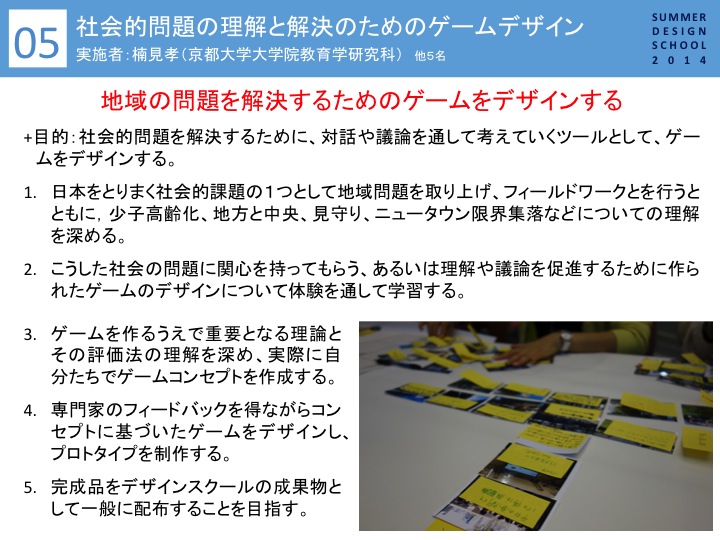テーマ
05 社会的問題の理解と解決のためのゲームデザイン
関係者・関係組織
実施者
楠 見孝 (京都大学大学院教育学研究科)
松井 啓之(京都大学経営管理大学院)
高橋 雄介(京都大学大学院教育学研究科)
江間 有沙(京都大学白眉センター/情報学研究科)
大野 健彦(NTTサービスエボリューション研究所 )
石川 知夏(NTTサービスエボリューション研究所 )
楠 見孝 (京都大学大学院教育学研究科)
松井 啓之(京都大学経営管理大学院)
高橋 雄介(京都大学大学院教育学研究科)
江間 有沙(京都大学白眉センター/情報学研究科)
大野 健彦(NTTサービスエボリューション研究所 )
石川 知夏(NTTサービスエボリューション研究所 )
課題内容
本ワークショップでは社会的問題を解決するために,対話や議論を通して考えていくツールとして,ゲームをデザインすることを目的とする.最初に,日本をとりまく社会的課題の1つとして地域問題を取り上げ,少子高齢化,地方と中央,見守り,ニュータウン限界集落などについての理解を深める.次に,こうした社会の問題に関心を持ってもらう,あるいは理解や議論を促進するために作られたゲームのデザインについて体験を通して学習する.その後,ゲームを作るうえで重要となる理論とその評価法の理解を深め,実際に自分たちでゲームコンセプトを作成する.専門家のフィードバックを得ながらコンセプトに基づいたゲームをデザインし,プロトタイプを制作する.最終的には,完成品をデザインスクールの成果物として一般に配布することを目指す.
教育目標
社会問題解決についてのコミュニケーションに必要なことを学習する.また,複雑な地域問題を,わかりやすく誰でもプレイすることができるゲームデザインに落とし込むときの視点や手法についての理解を深める.さらに,制作物が実際にプレイに耐えられるのか,またそのゲームプレイ後の行動や意識変化の測定方法など評価に関する観点を学習することで新たな問題発見や提案を行う力を身につける.
デザイン理論
- 学習環境のデザイン
- 参加型デザイン
- ソーシャルデザイン
デザイン手法
- ゲーミング・シミュレーション
- ブレーンストーミング・発想法
- デザイン評価,教育効果の評価法
- ダーティプロトタイピング
- フィールド調査手法
スケジュール
一日目
午前
イントロダクション
イントロダクション
- アイスブレーキング・自己紹介
- 目標の明確化:ゲーム・ツールの目的や必要性
- 地域課題とくに,少子高齢化,地方と中央,見守り,限界集落などの問題の提示,ゲームと実践,評価法の紹介
午後
フィールド調査(外出します)
フィールド調査(外出します)
- フィールド調査と気づきの整理
- ゲーム作成の基本についてのミニ講義と質疑
ニ日目
午前
作業
作業
- ブレーンストーミングを行い,ゲームコンセプトや参加者対象者を立案
- ゲームのコンセプトのプロトタイプの作成
午後
- ゲーム(最終プロトタイプ)の作成
三日目
午前
発表準備
発表準備
- ゲーム(最終プロトタイプ)の仕上げ
- 発表会のプレゼンの準備
午後
- プレゼンテーション